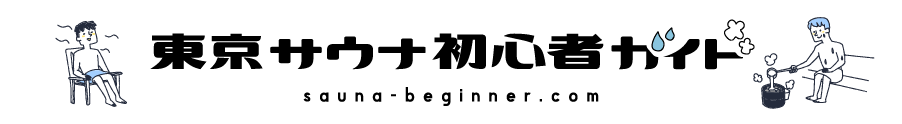「サウナって、最近では『ととのう』ってよく聞くけど、昔はもっと単純なものだったよね」。そんな風に感じる人、多いと思います。
現代のサウナは「ととのう時間」として人生に欠かせない存在になりましたよね。
でも、昔はまるで違う使われ方をしていました。
今回は、単純に「汗をかく」から、感覚を味わう文化へと変化した「サウナの完成の進化」について解説していきます。

第1次ブーム:汗と根性の時代
昔は「とにかく汗さえかけば体に良い」サウナはそんな場所でした。
暑い部屋でじっと耐えているだけで、達成感を感じるような雰囲気がありましたよね。
感覚よりも体感価値がすべて、精神的にも義務っぽさすらあった時代。
サウナは「頑張って入る場所」そんなイメージが強い時代でした。
今のサウナ:心で感じる場所
第1次ブームの頃と違い、現代では「どれだけ気持ちよく感じられるか」が大切になりました。
熱に打たれて体がゆるんでいく感覚、この時間をどう味わうかがポイント。
そのため、ただ汗をかくだけではなく「ととのう」や「リセット感」といった言葉が自然と
出てきました。
気持ちの解放や安らぎがサウナの中心になっている印象を受ける人も多いのではないでしょうか。
比較①:義務感vs感覚的
昔は「終業後に汗でもかいてスッキリしよう」くらいの目的で、サウナが日課のようになっていました。
言ってみれば「やらなきゃ感」のある健康ルーティーン。
一方、今はあえて予定を空けてでも「気持ち良さを味わいたい」と思う場所として捉えられています。
目的が「汗」から「気持ち良さ」に変わってきたのは、感覚重視の文化の証拠かもしれません。
比較②:熱と耐えるvs心地よさと心の動き
昔は熱さと向き合う時間を割り切って、「熱いのが常識」というところがありました。
しかし、今は「湿度・温度・静けさ」こそが大事で、五感が刺激されることを楽しむ傾向に変わっています。
言葉にすると難しいですが、サウナに入って「ああ、良い感じ」と思う瞬間の心の動きこそが、現代サウナの核心ではないでしょうか。
新しい楽しみ方の広がり
第1次ブームでは「サウナに入る=汗をかく」で完結していました。
しかし、今は水風呂や外気浴を含めた「1つの流れ」を大事にするようになっています。
さらにその後の「サウナ飯」や「クラフトドリンク」までが楽しみの一部。
サウナに行くことが単なる入浴行為ではなく、1日のイベントやレジャーになったわけです。
しかもその楽しみ方は多種多様。
「静かに1人でサウナを堪能する人」もいれば、「サウナの時間を仲間とシェアする」人もいます。
第1次ブームにはなかった幅の広さが現代のサウナ文化を支えていて、現代のサウナブームにも繋がっているようです。
サウナ施設の雰囲気も大きく変化
第1次ブームの頃のサウナ施設といえば、照明は暗めで、無骨なタイルや木材がむき出しのシンプルな造りがほとんどでした。
テレビの音が響く中で、おじさん達が黙々と汗を流すという空気感でしたが、今では間接照明やBGMでリラックスできる空間が当たり前。
フィンランドを意識した北欧風のデザインや、自然素材を活かしたインテリアも増えています。
「汗をかく場所」から「居心地のよさを追求した場所」へ変化し、空間づくりそのものがサウナ体験を引き立てる重要な要素になったのです。
まとめ
第1次サウナブームは「健康と根性」の象徴、現代の第3次ブームは「気持ちよくととのう」という違いが明らかです。
さらに現代は、水風呂や外気浴を組み合わせて心身をリフレッシュする「体験型」の文化へと成長しました。
汗より心の「ととのい」を求める今、一人ひとりが感じる「サウナの感覚」こそが、昔とはまったく違う文化の姿です。
次回は、そんな「感覚的なサウナ」がどのように広まっていったのか掘り下げていきます。