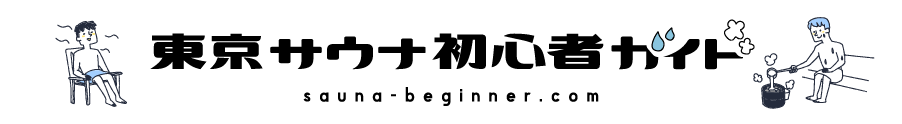1990年代から2000年代前半にかけて、日本では第二次サウナブームが訪れました。
第一次ブームが「おじさんの健康法」だったのに対し、この時代はスーパー銭湯や健康ランドが全国に広がり、家族や女性も楽しめるようになったのが特徴です。
サウナは「熱さに耐える場」から「癒しを味わう場」へ。
今回は、そんな第二次サウナブームを振り返りながら、今のサウナ文化との違いも見ていきましょう。

第二次サウナブームとは?
第二次サウナブームは1990年代〜2000年代前半にかけて起きた動きです。
バブル経済の崩壊後、人々は物質的な豊かさよりも「心の癒し」を求めるようになりました。
その流れに乗って広がったのが、スーパー銭湯や健康ランドといった大型温浴施設です。
ここではお風呂やサウナだけでなく、食事や休憩、マッサージまで楽しめる「ワンストップ癒し空間」が提供されました。
サウナはその中の一要素として組み込まれ、誰もが気軽に楽しめる存在へと変わっていったのです。
ブームを支えた施設の広がり
第二次ブームを語るうえで欠かせないのが、施設の形態の変化です。
サウナ単体ではなく、複合施設の一部として広まったことで、利用者層もぐっと広がって行きました。
スーパー銭湯の誕生と普及
1990年代前半から各地に登場したスーパー銭湯は、サウナ文化を一気に身近にしました。
大浴場に加えてサウナや露天風呂、食事処、休憩スペースまでがそろい、家族で一日中楽しめる施設として人気を集めます。
それまでのサウナは「会社帰りにおじさんが寄る場所」という印象でしたが、スーパー銭湯によって「休日のレジャー」としても定着。
サウナが日常生活の中に溶け込み、世代を問わず体験できるようになったのです。
健康センター・温浴施設の多様化
一方で、健康ランドや大型温浴施設も進化を遂げます。
サウナだけでなく、カラオケ、ゲームコーナー、マッサージチェアなどの娯楽が揃い、泊まり込みで過ごせる施設も珍しくありませんでした。
サウナはその中の「選択肢のひとつ」として位置づけられ、より気軽に利用される存在に。
昔のように「熱さに耐える根性の場」ではなく、「のんびり過ごす施設の中の1コーナー」として親しまれるようになったのが特徴です。
利用者の拡大と女性の参入
第一次ブームが男性中心だったのに対し、第二次では女性や家族連れが目立つようになりました。
特に女性専用サウナや岩盤浴、エステを組み合わせた施設が登場したのは大きな変化です。
「美容やダイエットにいい」といった切り口で女性誌にも取り上げられ、若い世代にも広がっていきました。
さらに子供と一緒に楽しめるスーパー銭湯の存在が、サウナを「家族で行ける場所」に押し上げたのです。
利用者層の幅広さこそが、このブームを支える原動力でした。
癒し文化との融合
バブル崩壊後の日本では、「癒し」というキーワードが社会全体に広がっていました。
アロマやマッサージ、スパといったリラクゼーション文化が注目される中で、サウナも「癒しの時間」を提供する一つの手段として再評価されます。
第一次ブームが「頑張るためのリフレッシュ」だったのに対し、第二次ブームは「休むための癒し」。
熱さや汗に耐えることよりも、心身を緩めてのんびり過ごすことが重視されました。
この空気感が、現代のサウナ文化にも繋がっているのです。
サウナ施設の雰囲気の変化
施設そのものの雰囲気も大きく変わりました。
第一次のサウナ施設はテレビと蛍光灯、無骨なタイル張りが当たり前でしたが、第二次ブームの頃になると一変。
照明を落としたり、木材や石材を取り入れて落ち着いた空間が増えてきました。
BGMやリラックスチェアの導入など、「居心地の良さ」が重視されるようになったのです。
これによって、サウナは汗を流すだけでなく、心地よく長時間過ごせる空間へとシフトしていきました。
第一次・第三次との違いを比較
第二次ブームは第一次、そして現在の第三次と比べても独自の特徴を持っています。
第一次は「男性中心・根性で汗をかく」スタイル。
第三次は「ととのう」をキーワードにサウナそのものが主役です。
対して第二次は「複合施設の一部としてのサウナ」。
つまり、主役ではなかったものの、裾野を広げたのが第二次の大きな功績です。
家族連れや女性にサウナを体験させ、気軽に楽しめる文化を根付かせたことが、今の第三次ブームへの橋渡しになったといえるでしょう。
まとめ
第二次サウナブームは、サウナを「特別なもの」から「誰もが気軽に楽しめるもの」へと広げた時代でした。
スーパー銭湯や健康ランドの普及、女性や家族層の参入、そして癒し文化との融合によって、サウナは日常のレジャーとして定着します。
この流れがなければ、現在の「サウナが主役の第三次ブーム」は生まれなかったかもしれません。
次回は、その第三次ブームがどのように始まり、なぜここまで盛り上がったのかを見ていきます。