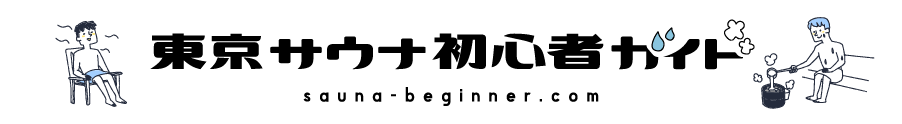サウナに入った後、水風呂を経て外気浴に身を委ねることを多くのサウナーが「ととのう」と表現します。
しかし、初心者のうちは「なんとなく気持ちいい」で済ませてしまうことも多いでしょう。
外気浴の体感を自分なりの言葉にすれば奥深さに気付き、呼吸や姿勢の工夫で「質の高いととのい」を得ることが可能です。
今回は、外気浴での感覚を言語化しながら、呼吸法や姿勢の工夫を通じて初心者から中級サウナーへステップアップする方法を紹介いたします。

そもそも「ととのう」とはどういう状態?
サウナ愛好家の間で定着している「ととのう」という言葉。これは医学的な専門用語ではなく、サウナ―が共通して感じる体験を表した俗語です。
一般的にはサウナと水風呂を繰り返した後に訪れる、心身のリラックスと高揚感が同居する状態を指します。
生理学的に見れば、サウナで交感神経が優位になり、水風呂で一気に血管が収縮。その後、外気浴に移ると副交感神経が働き、全身が緩む。この切り替えが、いわゆる「ととのう」感覚をもたらすのです。
初心者がよく口にする「体がふわふわする」や、「頭がすっきりする」といった表現も、この自律神経の変化と血流の安定によるものだと考えられます。
外気浴の体感を言葉にしてみる
外気浴は、火照った体を涼しい風にさらし心地よい脱力感を感じながら休む時間です。
しかし、その感覚は人によって微妙に違うため、自分なりに体感を言葉にしてみましょう。
・火照った肌に当たる風が「すっと染み込む」感覚
・鼓動が落ち着き、呼吸が「胸からお腹へとゆっくり広がる」感覚
・体全体が「椅子に沈み込む」ような脱力感
このような表現は、自分自身の「ととのい」を理解する手助けになります。
日記やスマホのメモに「今日は風が羽のようだった」「頭が透明になった気がする」と書き残すのも良い方法です。
感覚を記録することで、体調やコンディションによる違いにも気付きやすくなり、サウナが「ただの習慣」から「体験の探求」へと変わっていきます。
呼吸法で外気浴の質を高める
外気浴中は、呼吸に意識を向けることでより深いリラックスを得られます。ただ、サウナ後は心拍数がやや高めなので、浅い呼吸を繰り返しがちです。
ととのいやすくするには、意識的に深い呼吸に切り替えて、副交感神経を優位にすることが重要になります。おすすめは「4秒吸って、6秒吐く」呼吸法。
息を吸うときに胸やお腹を大きく広げ、吐くときには肩や首の力を抜くように意識しましょう。
特に「吐く」動作を長めにすると、心拍数が落ち着きやすくなります。
また、口呼吸より鼻呼吸を意識するのもポイントです。
鼻呼吸は空気を加湿・加温して肺に取り込むため、乾燥を防ぎながらリラックス効果を高めてくれます。
呼吸に集中していると、周囲の雑音が気にならなくなり、外気浴の時間がより豊かなものになります。
姿勢の工夫でより深くととのう
外気浴は姿勢によって体感が大きく変わります。
よく見かけるのはリクライニングチェアやベンチに腰を掛けての休憩ですが、その際の姿勢を少し工夫してみましょう。
基本は「頭を心臓より少し高め」にすること。血流が安定しやすく、立ち眩みを防げます。足を肩幅に軽く開き、両腕を楽に下ろすか椅子のひじ掛けに預け、肩の力を抜いてみましょう。
施設によっては寝転んで外気浴できるスペースもあります。
全身を水平に預けると重力から解放されるような感覚が得られますが、混雑時はマナーを守ることも大切です。
また、自分にあった「ととのい椅子」を見つけるのも楽しみの1つ。
硬いベンチよりもリクライニングやハンモックに近い椅子の方がリラックスしやすい人もいます。
自分の「ととのい体験」を積み重ねる
外気浴をただの休憩時間にするのではなく、呼吸や姿勢を工夫し体感を言語化してみると、その時間はまったく別の価値を持つようになります。
言葉にすることで体験を客観視でき、呼吸と姿勢で質を高め、さらに次回のサウナに繋げることができるのです。
「今日は風が優しかった」「吐く息と一緒に緊張が抜けた」など、自分なりの言葉を積み重ねることで、「ととのいのアルバム」が出来上がっていきます。
そしてそれは、他のサウナ―と体験を共有したり、自分だけのととのい方を見つけるヒントにもなるでしょう。
まとめ
外気浴で「ととのう」感覚は、誰にとっても少しずつ違います。
だからこそ、自分なりに言葉にしてみることが中級サウナ―への第一歩です。
呼吸法でリラックスを深め、姿勢を工夫して体を委ねれば、外気浴の時間はただの休憩ではなく「ととのいの探求」へと変わります。
自分自身の体感を大切にし、サウナの奥深さを一層楽しんでみましょう。